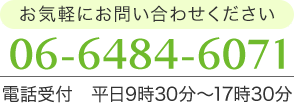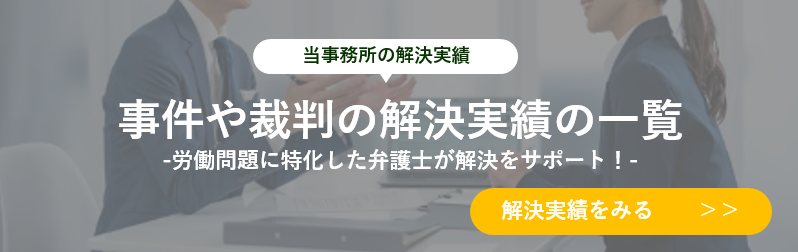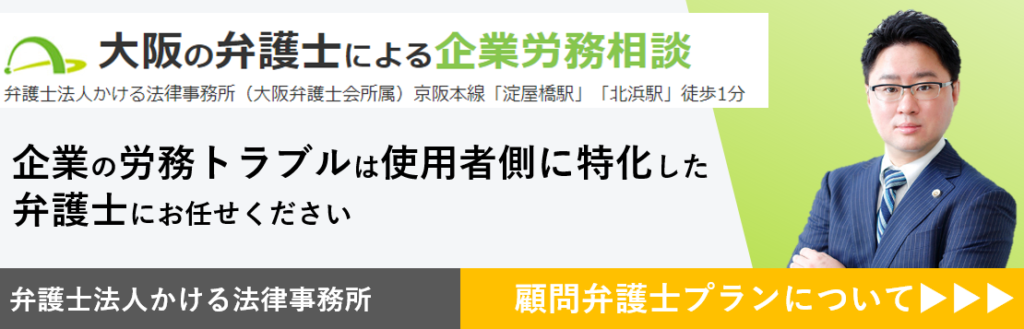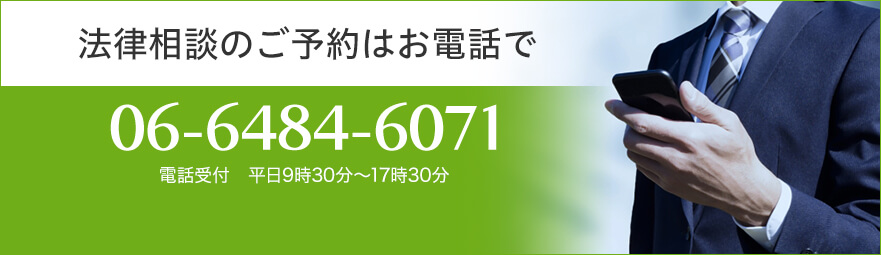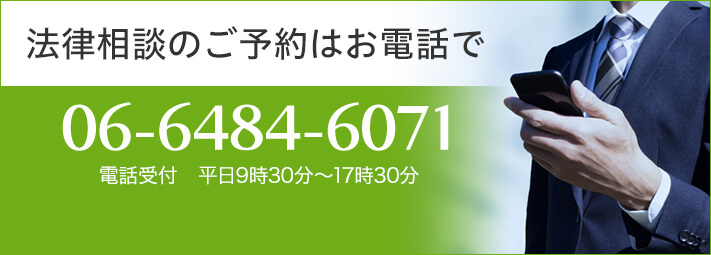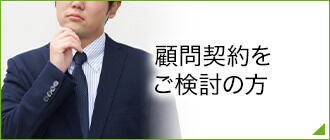退職後の損害賠償請求についてよくある相談例
①退職代行会社から退職通知が届き、従業員が引継ぎを行わず、退職した。
②重要なプロジェクトの途中で、リーダーが退職し、プロジェクトがとん挫した。
③他の従業員を大量に引き抜き、競業会社に転職した。
▼関連記事はこちらから▼
競業避止義務への対応方法について!退職後の従業員・誓約書・就業規則への対応
従業員の競業避止義務違反に基づく損害賠償請求を弁護士が解説します
従業員(労働者)の退職の自由と損害賠償請求
従業員(労働者)は、雇用契約を締結したとしても、職業選択の自由(憲法22条1項)が保障され、その一環として退職の自由も保障されています。
そのため、無期雇用契約(期間の定めがない雇用契約)では、従業員は、いつでも雇用契約の解約の申入れをすることができるとされ、解約申入日から2週間の経過によって雇用契約が終了するとされています(民法627条1項)。つまり、従業員は、2週間前に通知することによって退職できます。このルールは強行規定と解釈されているため、就業規則で、退職までの期間を2週間より延長する条項(例えば、1か月前の退職届の提出)があったとしても、2週間前の通知で退職できると解釈されています。
そのため、会社は、従業員が退職したこと自体を理由として、従業員に対して損害賠償を請求することはできません。
▼関連記事はこちらから▼
就業規則の作成・チェックについて弁護士が解説
雇用契約書(労働契約書)の作成のメリットとは?作成方法について弁護士が解説
モンスター社員(問題社員)の放置は危険?弁護士が会社にとって放置するリスクを解説!
引継義務違反に基づく損害賠償請求
従業員には、退職の自由が保障されていますが、その一方で、雇用契約期間中において誠実に労働する義務を負います。そのため、従業員は、誠実労働義務の内容の一つとして業務の引継ぎ等を誠実に実施する義務(引継義務)を負います。
そのため、従業員が引継義務等に違反して、会社に損害賠償を与えた場合、会社は、従業員に対して、損害賠償を請求できる可能性があります。
また、会社(使用者)は、従業員が業務の引継ぎを行わないまま無断で欠勤する等、従業員の誠実労働義務違反が著しい場合、懲戒処分や退職金不支給も可能です。
誠実義務違反に基づく損害賠償請求
従業員は、雇用契約期間中、殊更に会社の利益を侵害する行為を回避する誠実義務を負っています。
そのため、従業員による引抜行為が単なる転職の勧誘の域を超えて、社会的相当性を逸脱し、極めて背信的な方法で行われた場合、会社は従業員に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
他の従業員を大量に引き抜き、競業会社に転職したというケースでは、会社の重要な秘密情報も持ち出されている可能性もあるため、会社の重要な資産を守るためにも、従業員に対する損害賠償請求を検討すべき事例といえます。
▼関連記事はこちらから▼
従業員に対する懲戒処分とは?懲戒処分の種類や注意点を弁護士が詳しく解説!
会社が従業員に対して損害賠償請求を実施する際の注意点
①義務違反や損害の立証の困難性
従業員は会社に対して雇用契約期間中に引継義務を負いますが、会社が従業員に対して引継義務違反に基づく損害賠償を請求するためには、ア)従業員が引継義務に違反したことやイ)引継義務違反によって損害が発生したこと(因果関係)を会社が主張、立証する責任を負います。
特に、完璧な引継を求めることは困難であるため、必要な範囲で引継ぎが行われていれば、引継義務違反を主張できないため、単に引継ぎが不十分だっただけでは、会社が従業員に対して損害賠償を請求することは困難です。
引継義務違反に基づく損害賠償請求の場合、引継義務違反があることや損害発生や因果関係の主張、立証が困難なこともあるため、従業員に対する損害賠償請求が認められない可能性があることを理解しておく必要があります。
②従業員による会社に対する請求(反訴)の可能性
ほとんどの従業員は、引継ぎ等を適切に行ったうえで退職します。それにもかかわらず、引継ぎ等を全く行わず、退職する従業員は、会社に対して不信感や恨みがあって、会社との間で何らかのトラブルを抱えている可能性もあります。
そのため、会社が従業員に対して損害賠償を請求する場合、従業員も会社に対して未払残業代や安全配慮義務違反(ハラスメント)に基づく損害賠償を求めてくる可能性もあります。
会社が従業員に対して損害賠償を請求する場合、従業員から逆に請求される可能性がないかどうかを事前に検討しておく必要があります。
▼関連記事はこちらから▼
バックペイとは?解雇裁判で主張されるバックペイの意味や計算方法を弁護士が解説します!企業側のリスクとは?
③未払給与と損害賠償請求権を一方的に相殺できないこと
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とされており(労働基準法24条1項・賃金全額払いの原則)、未払給与が存在するとしても、会社の従業員に対する損害賠償請求権を自働債権として一方的に相殺することができず、会社は、従業員に対して未払給与を支払わなければなりません。
会社の従業員に対する損害賠償請求権の存在が明らかな場合でも、従業員の同意なく、未払給与と相殺できないので注意しなければなりません。
退職後の従業員への損害賠償請求に関する当事務所の解決事例
退職した従業員による競業避止義務違反に対応した事例
退職した複数の従業員が、同一の商圏内において、会社と同様のサービスを始め、お客様(利用者)や取引先との接触を開始している。会社は、就業規則において退職後の競業避止義務を定めており、また、入社時・退職時に誓約書も取得している。退職した複数の従業員は、雇用契約に基づく競業避止義務に違反しており、何らかの対応ができないか。
退職した従業員による会社の知的財産権(知財)の侵害に対応した事例
会社から退職した従業員が独立し、新たに会社と同一のサービスを始め、店舗を開設した。競合するサービスを始めることは、事前に承諾していたものの、元従業員は会社の成果物(写真や画像)を利用し、広告や宣伝を行っていた。会社から元従業員に対してクレームを行ったが、誠実な対応がない。
退職代行会社による退職通知書に対応した事例
従業員と連絡を取ることができなくなっているが、ある日突然、退職代行会社(法律事務所)から退職通知書が届いたが、今後の対応方法がわからない。社内では批判や混乱が発生しており、どのように判断したらいいかわからない。
弁護士による退職後の従業員への損害賠償請求対応
従業員が労働契約に違反し、会社に損害を発生させた場合、会社による従業員に対する損害賠償請求を検討しなければならないことがあります。
弁護士は、紛争・訴訟対応や労働法に精通しており、重大なリスクを回避するため、また、損害の回復に向けて、従業員に対する損害賠償請求に際して、以下の対応が可能です。
①従業員に対する内容証明郵便(警告書)の送付
②従業員との裁判外交渉・和解交渉
③従業員に対する民事訴訟の提起
④刑事告訴(従業員に犯罪行為がある場合)
⑤従業員による未払残業代や損害賠償請求への対応
▼関連記事はこちらから▼
モンスター社員対応~問題社員対応、解雇・雇止めについて弁護士が解説~
残業代請求対応、未払い賃金対応について弁護士が解説
従業員が営業秘密や情報漏洩を行った場合について弁護士が解説
大阪で弁護士をお探しの情報通信業(IT業)の方へ
業務上横領が起きた際の会社の対応のポイントとは?刑事告訴は可能?-モンスター社員対応-
業務上横領で社員を刑事告訴できますか?弁護士が解説!
従業員に対する損害賠償請求については弁護士にご相談ください
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約では、問題社員対応、未払い賃金対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等)等の労働問題対応を行います。
Last Updated on 2024年6月18日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の中小企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の中小企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。

代表弁護士 細井大輔 
プロフィールはこちらから