タイムカードにおける労働時間管理の方法とは?未払い残業代について弁護士が解説
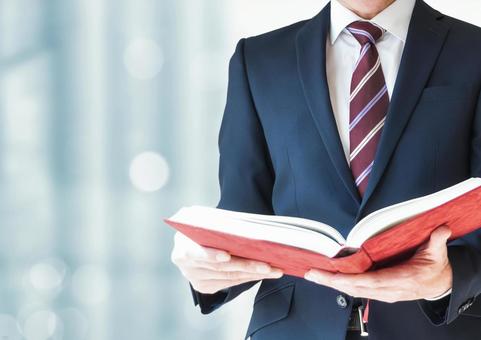
弁護士法人かける法律事務所では、企業における残業代請求対応・未払い賃金対応について、企業の皆様のニーズに基づいたサポート・支援を行っています。残業代請求対応・未払い賃金対応で悩み・不安のある企業(経営者様)は、是非、一度、当事務所にご相談ください。
労働時間とは?
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示によって労働者が業務に従事する時間をいいます。そのため、以下の時間も、原則として労働時間として取り扱う必要があります。
①使用者の指示により就業を命じられた業務に必要な準備行為
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められ、 労働から離れることが保障されていない状態における待機時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講
労働時間の適正な把握
労働基準法では、労働時間・休日・深夜残業等について規定しており、企業は、割増賃金(残業代)を計算するためにも、労働時間を適正に把握し、管理する義務を有しています。厚生労働省は、2017年1月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を定めており、労働時間の適性な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしています。
また、2019年4月施行の「働き方改革関連法案」に従い、管理監督者に対しても労働時間を把握することが必要となりました。つまり、労働安全衛生法では、一定の残業時間を超える労働者に対し、医師による面接指導を義務づけており(同法66条の8の2)、面接指導の要否を判断するため、労働時間の状況を把握しなければなりません(同法66条の8の3)。対象労働者には,、管理監督者の他に、裁量労働者も含まれます。
以上のとおり、時間外労働の上限規制(三六協定)に違反していないかの確認や労働基準法で定められた割増賃金の適正な計算のためだけでなく、労働安全衛生法上の義務を守るためにも、各企業には労働時間の適性な把握が必要となります。労働基準法や労働安全衛生法に違反し、立入調査や行政指導に発展するケースも実際にあります。
企業は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業時刻・就業時刻を確認し、これを記録する必要があります。
▼関連記事はこちらから▼
固定残業代制度の明確区分性とは?企業が知っておくべきポイントについて、弁護士が解説します。
企業が固定残業代制度を導入するに際して、注意すべきポイントについて、弁護士が解説します。
タイムカード利用による労働時間の把握
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間の把握方法として、以下の方法を例示しています。
①使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること
②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
③自己申告。ただし、上記①又は②の方法によることなく、これを行わざるをえず、必要な措置を講じた場合に限る。
労働時間の把握方法として、タイムカードは、よく利用される方法です。実際に、多くの企業がタイムカードを導入し、労働時間管理を行っているのではないでしょうか。
▼関連記事はこちらから▼
未払残業代を請求されたときに企業が対応すべきことについて、弁護士が解説します。
勤務開始前の準備時間や勤務開始後の後片付け時間は労働時間ですか?労働時間の把握の注意点を弁護士が解説します。
【2024年4月改正】専門業務型裁量労働制の対象となる業務や改正内容を弁護士が解説します
【2024年4月改正】企画業務型裁量労働制の改正や注意点を弁護士が解説します。
労働時間管理におけるタイムカードの注意点
①タイムカードの打刻時間=労働時間ではない場合
タイムカードで打刻された始業時刻が出社時刻(≠始業時刻)である場合やタイムカードに打刻された終業時刻が退社時刻(≠終業時刻)である場合、タイムカードの打刻時間≠労働時間となり、タイムラグが生じることがあります。
もっとも、裁判所で残業代請求が問題となる場合、裁判所は、タイムカードの打刻時間を重要な証拠として評価するため、企業側がこのタイムラグを客観的証拠で立証できない場合、タイムカードの打刻時間に従い、残業代請求が認められてしまうことがあります。
そのため、タイムカードの打刻時間=労働時間ではない場合、トラブル・紛争を回避するためにも、タイムカードの打刻時間と労働時間が一致するように打刻方法を管理する必要があります。
また、それが難しい場合でも、タイムカードの打刻時間=労働時間ではないことを示す客観的証拠を準備しておく必要があります。これが難しい場合、タイムカードによる労務時間の管理方法について見直しを検討するべきでしょう。
▼関連記事はこちらから▼
【令和6年4月16日最高裁判決】技能実習生の指導員の事業場外労働のみなし労働時間制度の適用に関する最高裁判決について弁護士が解説します。
②タイムカードによる労働時間の管理が難しい場合
タイムカードによる労働時間の管理が難しい場合(例えば、直行・直帰が多い)、タイムカード以外の選択肢も検討してみる必要があります。
ただ、現実には、各企業の実情やこれまでの慣習から、タイムカードが利用される場合があります。もちろん、これまでの方法を変えることは簡単なことではありません。ただ、裁判所は、タイムカードによる労働時間の認定を重視するため、残業代請求のリスクを理解する必要があります。
特に、最近の法改正により、2020年4月1日以降、残業代や未払い賃金の消滅時効(請求期間)は2年間から5年(当面の間は3年)に延長されました。例えば、請求期間が3年となると、従業員1名につき、毎月8万円の未払い残業代が発生している場合、最大192万円(8万円×24か月)から最大288万円(8万円×36か月)に増加し、最大96万円/名の負担増となります。しかも、請求期間が5年となると、最大480万円(8万円×60か月)となり、最大280万円/名の負担増となります。
また、2023年4月1日以降、大企業だけでなく、中小企業においても、月60時間超の残業割増賃率が25%から50%に引き上げられます。このような法制度の改正によって、残業代や未払い賃金トラブルに巻き込まれるリスクや経済的な負担は増加しています。
タイムカードによる労働時間の管理が難しい場合、タイムカード以外の方法で、労働時間の管理方法を検討するべきです。最近では、クラウド勤怠管理システムも普及しています。勤怠管理の方法を変更することによって、残業代請求のリスクや従業員との紛争・トラブルを未然に回避できます。
③管理監督者の労働時間の把握
管理監督者は、労働基準法の労働時間規制が適用されないため、企業が十分に検討することのないまま、労働基準法上の「管理監督者」に該当すると判断し、出社時刻や退社時刻をそのままタイムカードに打刻させるケースがあります。
ただ、裁判では、労働基準法上の「管理監督者」の該当性については、肩書や職位だけではなく、対象となる労働者の立場や権限を踏まえて、実質的に判断します。そのため、裁判において、対象となる労働者が管理監督者であることが否定された場合、タイムカードの打刻時間を基準に、未払い残業代請求が認められてしまうことがあります。
そのため、管理監督者であっても、労働時間の管理の必要性は変わらず、タイムカードによる労働時間の管理が難しい場合、管理方法の変更を検討する必要があります。
④タイムカードによる労働時間管理が煩雑であるため、労働時間の管理を行っていない場合
タイムカードによる労働時間管理は煩雑であることは確かです。また、タイムカードの打刻時間=労働時間と認定されてしまうリスクがあるため、そもそも労働時間の管理を行わないという企業もあるかもしれません。
もっとも、企業には労働時間を把握する義務があるため、労働時間の管理を行わないこと自体にも一定のリスクがあります。例えば、労働時間の把握を怠ると、従業員の一方的な主張・証拠(メモ・日記・通信記録)に従い、残業代請求が認められてしまうこともあります。
労務時間の把握が企業の責務であることを理解したうえで、各企業の実情に応じた労務管理を行うことが必要となります。タイムカードによる労働時間管理が煩雑であったとしても、他の方法(例えば、クラウド勤怠)を検討し、労働時間の管理を検討するべきです。
▼関連記事はこちらから▼
スシローに対する労基署による是正勧告(5分未満の労働時間の切捨て)から適切な労働時間の管理について弁護士が解説します。
労働時間管理/未払い残業代問題については弁護士にご相談を
弁護士への相談例:
①労働実態と異なるタイムカードに基づいて残業代を請求されている。
②労働時間の把握方法がわからない。
③管理監督者から残業代を請求されている。
④タイムカードを含む労働時間の管理方法を変更したい。
⑤クラウド勤怠管理システムを導入したいが、労働基準法に適合する運用方法がわからない。
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。 残業代請求対応・未払い賃金対応に関する労働問題について、お悩みや不安がある企業(経営者)の皆様は、是非お問い合わせいただき、ご相談ください。
関連記事
- 未払残業代対応~移動時間と労働時間との区別について、企業側の視点から弁護士が解説します~
- 仮眠時間は労働時間?残業代を支払う際の注意点とは?仮眠時間の労働時間該当性について、弁護士が解説します。
- 不活動時間とは?12時間または24時間シフトで実作業がない時間帯について労働時間性を否定した裁判例について、弁護士が解説します~東京地判平成20年3月27日~
- 未払残業代を請求されたときに企業が対応すべきことについて、弁護士が解説します。
- 企業が固定残業代制度を導入するに際して、注意すべきポイントについて、弁護士が解説します。
- 固定残業代制度の注意点とは?企業が知っておくべき固定残業代制度(対価性の要件)について、弁護士が解説します。
- 固定残業代制度の明確区分性とは?企業が知っておくべきポイントについて、弁護士が解説します。
- 労働法研究会(未払残業代請求の実務対応)を開催しました。
- 【令和6年4月16日最高裁判決】技能実習生の指導員の事業場外労働のみなし労働時間制度の適用に関する最高裁判決について弁護士が解説します。
- 労働法研究会(2024年問題の課題と対応策-時間外労働の上限規制-)を開催しました。

