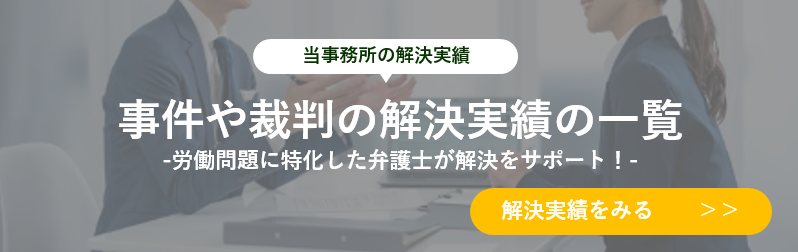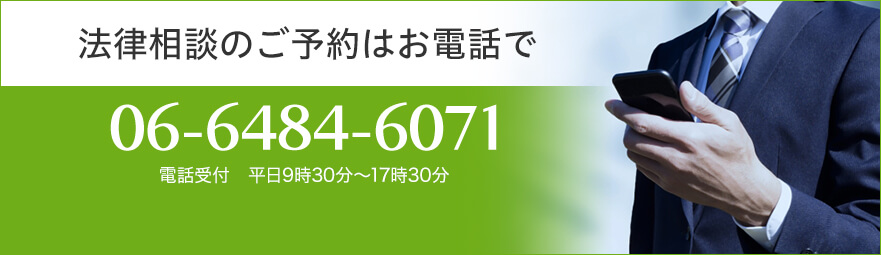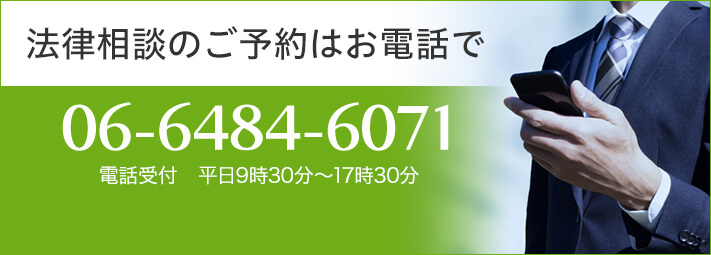最高裁判決のポイント
①事業場外労働のみなし労働時間制度(労働基準法38条の2第1項)の適用(「労働時間を算定し難いとき」)の可否について、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すべきと判断しました。
②業務日報による報告のみを重視して、「労働時間を算定し難いとき」に当たると判断した原審(控訴審判決)について、労働基準法38条の2第1項(本件規定)の解釈適用を誤った違法があると判断しました。
③業務日報が提出されているケースでは、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討する必要があると判断しました。
争点
事業場外労働のみなし労働時間制度(労働基準法38条の2第1項)における「労働時間を算定し難いとき」の判断基準や判断要素
労働基準法38条の2第1項
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
事業場外労働のみなし労働時間制度とは?
労働時間は、実際の労働時間(実労働時間)によって算定することが原則です。
事業場外労働のみなし労働時間制度とは、従業員が事業場外で業務に従事した場合、その労働時間を算定し難いときは、一定の労働時間を業務に従事したものと「みなす」という制度です(労働基準法38条の2第1項)。
「みなす」という制度であるため、この制度の適用が認められると、実労働時間と関係なく、みなされた労働時間数に従って時間外労働の有無が判断されることになります。
つまり、従業員が業務の全部又は 一部を事業場外で従事し、会社の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合は、労働時間のみなし制度を採用することによって、会社の労働時間の算定義務が特別に免除されることになります。
この制度は、実労働時間の算定の原則に対する例外的な制度であるため、①事業場外で従業員が業務に従事し、②会社の具体的な指揮監督が及ばず、③労働時間の算定が困難な業務に限られます。例えば、取材記者や外勤営業社員への適用が想定されています。
事業場外労働のみなし労働時間制度が適用できないケースの例
・複数名のグループで事業場外労働を行う場合で、そのグループの中に労働時間を管理する立場にある者がいる場合
・無線やポケットベル等で会社の指示を随時受けながら、事業場外で労働する場合
・事業場において、具体的な当日の業務指示(訪問先、帰社時刻等)の後、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合
本判決の事案の概要
1 上告人(会社)
上告人は、外国人の技能実習に係る監理団体です。
2 被上告人(従業員)
被上告人は、平成28年9月、上告人に雇用され、指導員として勤務したが、同30年10月31日、上告人を退職しました。
被上告人は、自らが担当する九州地方各地の実習実施者に対し月2回以上の訪問指導を行うほか、技能実習生のために、来日時等の送迎、日常の生活指導や急なトラブルの際の通訳を行うなどの業務に従事していました。
3 被上告人の業務の状況
(1)被上告人は、本件業務に関し、実習実施者等への訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理していました。
(2)被上告人は、上告人から携帯電話を貸与されていましたが、これを用いるなどして随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることはありませんでした。
(3)被上告人の就業時間は午前9時から午後6時まで、休憩時間は正午から午後1時までと定められていましたが、被上告人が実際に休憩していた時間は就業日ごとに区々でした。
(4)被上告人は、タイムカードを用いた労働時間の管理を受けておらず、自らの判断により直行直帰することもできましたが、月末には、就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報を上告人に提出し、その確認を受けていました。
原審(控訴審判決)の要旨
被上告人の業務の性質、内容等からみると、上告人が被上告人の労働時間を把握することは容易でなかったものの、上告人は、被上告人が作成する業務日報を通じ、業務の遂行の状況等につき報告を受けており、その記載内容については、必要であれば上告人から実習実施者等に確認することもできたため、ある程度の正確性が担保されていたといえる。
現に上告人自身、業務日報に基づき被上告人の時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったものであり、業務日報の正確性を前提としていたものといえる。
以上を総合すると、本件業務については、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。
本判決(最高裁判決)
「本件業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等、多岐にわたるものであった。また、被上告人は、本件業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものといえ、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったものである。
このような事情の下で、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、被上告人が担当する実習実施者や1か月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、上告人において、被上告人の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い。」
「原審は、被上告人が上告人に提出していた業務日報に関し、①その記載内容につき実習実施者等への確認が可能であること、②上告人自身が業務日報の正確性を前提に時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったことを指摘した上で、その正確性が担保されていたなどと評価し、もって本件業務につき本件規定の適用を否定したものである。
しかしながら、上記①については、単に業務の相手方に対して問い合わせるなどの方法を採り得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明らかでない。
上記②についても、上告人は、本件規定を適用せず残業手当を支払ったのは、業務日報の記載のみによらずに被上告人の労働時間を把握し得た場合に限られる旨主張しており、この主張の当否を検討しなければ上告人が業務日報の正確性を前提としていたともいえない上、上告人が一定の場合に残業手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正確性が客観的に担保されていたなどと評価することができるものでもない。」
「以上によれば、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈適用を誤った違法があるというべきである。」
本判決(最高裁判決)の補足意見
「いわゆる事業場外労働については、外勤や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレワークの局面も含め、その在り方が多様化していることがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認められるか否かについて定型的に判断することは、一層難しくなってきているように思われる。
こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があるものと考える。」
本判決の検討と評価~企業に与える影響を踏まえて~
①最判平成26年1月24日(阪急トラベルサポート事件)との関係
事業場外労働のみなし労働時間制度のリーディングケースといわれる最判平成26年1月24日(阪急トラベルサポート事件)は、「本件添乗業務について,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。」とし、このような「業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。」としている。
本判決でも、「業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮」して、「被上告人の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い」と判断しており、本判決と最判平成26年1月24日(阪急トラベルサポート事件)は、矛盾するわけではなく、新たな判断基準を示したものではないと思われる。
②本判決の意義
佐々木 宗啓ほか編著・類型別労働関係訴訟の実務[改訂版]Ⅰ・236頁【水倉義貴】では、「事業場外労働における業務内容等が記載された日報等が作成、提出される場合でも、その内容がもっぱら労働者に委ねられ、正確性を担保する方法がなく、また、正確性について使用者側が確認する手段もないという場合には、報告内容の正確性について使用者が把握することはできないのであるから、前記の日報等が作成、提出されることをもって、「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとすることは、実態とかけ離れ、「労働時間を算定し難いとき」に当たる事態がほとんどないことを意味するものであり、制度が設けられた趣旨を失い、妥当でないように思われる」とされ、「その作成内容がもっぱら労働者の裁量に委ねられている日報等に業務内容や時間等が記載されていることのみをもって「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとすることは妥当でなく、何らかの方法によりその正確性を担保する手段があり、又は正確性を確認できるような手段があることまで必要と解すべきである」と指摘されている。
本判決は、「業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとした」原判決(控訴審判決)を批判するものであって、上記文献で指摘している趣旨やポイントと一致する。
本判決は、業務日報が作成されているだけでは、直ちに事業場外労働のみなし労働時間制度の適用が否定されるわけではないことを確認した点で重要な意義がある。
③事業場外労働のみなし労働時間制度に与える影響
事業場外労働のみなし労働時間制度の適用の可否を判断する裁判例では、その適用を否定する裁判例が多くある。例えば、同制度の適用を否定する裁判例として、東京地判平成22年10月27日(レイズ事件)、東京地判平成24年10月30日(ワールドビジョン事件)、東京地判平成27年9月18日(落合事件)等がある。そのため、事業場外労働のみなし労働時間制度の適用は厳格に判断・運用される傾向にあるものの、本判決は、業務日報による報告のみを重視すべきではないことを明確にした。
今後は、事業場外労働のみなし労働時間制度を導入している会社において、業務日報を求めるだけでは、直ちに同制度の適用が否定されるわけではなく、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情によってケースバイケースで判断されることになり、同制度を導入する企業に影響を与えることになる。
未払残業代請求については、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください。
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約では 問題社員(モンスター社員)対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争対応(解雇・雇止め、残業代、ハラスメント等)、労働審判・労働裁判対応、雇用契約書・就業規則対応、知財労務・情報漏洩、等の労働問題対応を行います。
▼弁護士による対応はこちらから▼
残業代請求対応、未払い賃金対応について弁護士が解説
Last Updated on 2024年8月14日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。

代表弁護士 細井大輔 
プロフィールはこちらから