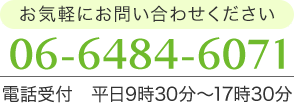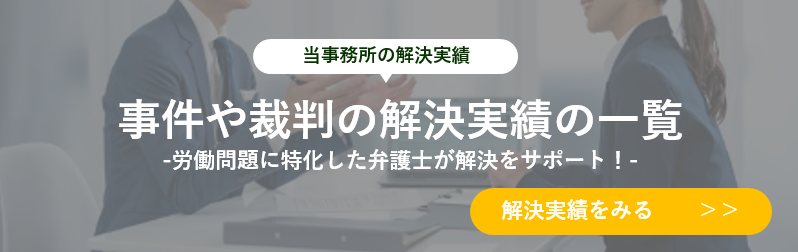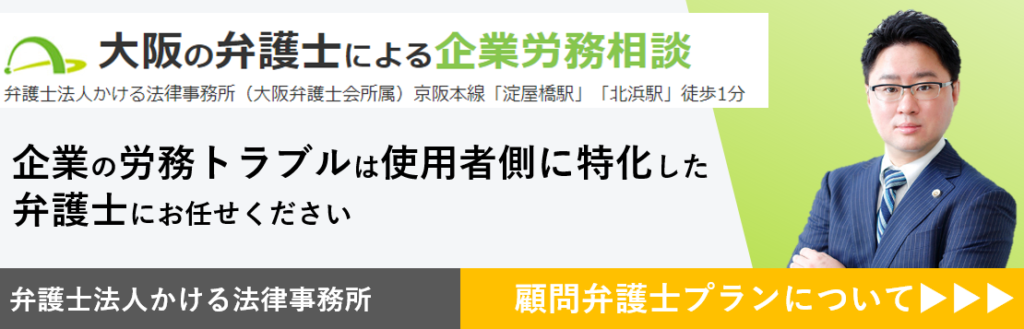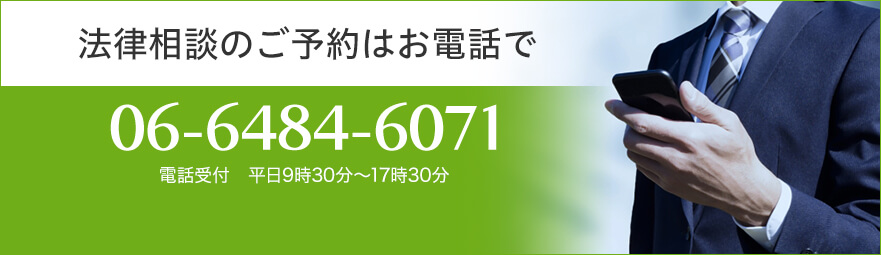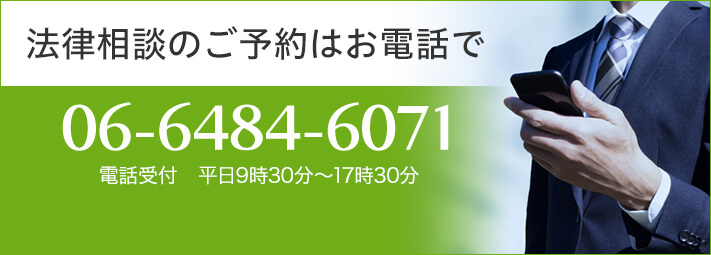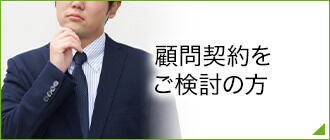よくある相談
①業務委託契約を結んでいるが、発注先のエンジニアにこちらが直接指示を出している。これって違法になるのか?
②自社でPCやアカウントを貸与し、委託先のエンジニアを常駐させているが問題はないか?
③SES契約でエンジニアを受け入れていたが、本人が『自分は派遣だ』と訴えてきた。
偽装請負とは?
偽装請負とは、形式上は注文者(発注者)と請負業者(受託者)との間で請負契約又は委任契約(業務委託契約)が締結されているものの、実態としては発注者が受託者の雇用する労働者に対し、直接具体的な指揮命令を行って作業をさせているような場合をいいます。これは、契約の形式にかかわらず、実質が「労働者派遣」(*)であるため、労働者派遣法に違反します。
*労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」をいい、発注者と受託者の従業員との間に指揮命令関係が生じていることがポイントとなります。
厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」について
偽装請負のリスク
偽装請負は、請負業者(受託者)にとっても、注文者(発注者)にとっても、法的なリスクがあります。
【請負業者(受託者)のリスク】
①労働者派遣法に基づく行政指導又は改善命令等
②請負業者(受託者)が労働者派遣事業の許可を有しない場合、刑事罰
【注文者(発注者)のリスク】
①労働者派遣法に基づく行政指導、勧告又は公表
②労働者派遣法に基づく派遣先の義務に違反している場合、刑事罰
③注文者(発注者)と請負業者(受託者)の従業員との間で雇用契約が成立したものとみなされる可能性があること(労働契約申込みなし制度・労働者派遣法第40条の6第1項5号)
▼偽装請負に関する関連記事▼
偽装請負とは? 違法となるケースと適正な業務委託のポイントについて、弁護士が解説します。
IT業界で偽装請負が問題となる理由
IT業界では、システム開発や保守運用等を、外部のエンジニアに委託する形で業務を進めることがあります。特に、SES(システムエンジニアリングサービス)契約や業務委託契約が広く用いられていますが、その運用が適切でない場合、「偽装請負」として法令違反とされることがあります。
特に、IT業界では、プロジェクトごとに人材を柔軟に確保する必要があるため、SES契約が活用される一方で、業務指示や勤務管理等の実態が契約と一致しないケースがあります。
そのため、形式上は業務委託契約であっても、実態が「派遣」にあたる場合には、偽造請負と判断される可能性があります。
また、IT業界では人手不足や納期の厳しさから、現場の実情が軽視されやすく、コンプライアンスが後回しになる傾向もあります。こうした構造的な事情も、偽装請負が問題となりやすい背景の一つといえます。
IT業界で起きる偽装請負トラブルとは?事例で学ぶ法的リスク
事例①ー大手SIerと下請企業間のSES契約に関する偽装請負の指摘
ある大手SIer(システムインテグレーター)は、下請企業とSES契約を締結し、常駐エンジニアを多数プロジェクトに受け入れていましたが、実態として、以下のような状況がありました。
- 元請企業のプロジェクトマネージャーが常駐エンジニアに直接業務を指示
- 勤怠報告が元請企業に直接送られていた
- 作業内容が日々変化し、受託企業側で管理していなかった
このような運用があると、労働基準監督署が偽装請負の疑いで調査を行う可能性があり、元請企業としては、是正指導を受けるリスクがあります。
事例②ーエンジニアによる「自分は派遣だ」という労働局への申告・相談
SES契約で他社に常駐していた若手エンジニアが、自社ではなく常駐先の社員から直接指示を受けていたことに違和感を抱き、労働局に「実態は派遣労働だ」と相談した事案。
この場合、労働局が相談を踏まえて調査を行い、発注元企業と受託企業に対し、契約の適正化と実態の是正指導がなされる可能性があります。
事例③ー元受企業による業務委託契約の解除に伴う労働紛争・訴訟への発展
SES契約で常駐していたエンジニアとの契約がプロジェクト終了とともに一方的に打ち切られ、「実態は労働契約だった」として、エンジニアから労働者性の確認を求める訴訟を提起されるリスクがあります。
偽装請負の判断基準やポイント
IT業界をはじめとする多くの企業で活用されている「業務委託」や「SES(準委任)契約」ですが、契約の形は適法であっても、現場での運用次第では「偽装請負」として違法と判断される可能性があります。
特に労働者派遣との違いを正確に理解していないまま実務を進めると、企業側にとって大きなリスクとなります。契約の形式ではなく“実態”に基づいて判断される偽装請負について、具体的な判断基準やポイントを解説します。
偽装請負の判断基準は、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)において示されており、請負業者(受託者)と注文者(発注者)との間の業務委託契約書(請負契約書)の文言のみならず、実態を踏まえて判断されます。
偽装請負の判断基準のポイントは、以下のとおりです。
①請負業者(受託者)が雇用する従業員の労働力を自ら直接利用すること(直接利用)
・業務の遂行方法に関する指示
・業務遂行の評価等に関する指示
・労働時間等(始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇等)に関する指示
・配置の決定及び変更に関する指示
・服務規律に関する指示
②請負契約に基づく請負業務を請負業者(受託者)自身の業務として、発注者から独立して処理するものであること(独立性)
・業務処理のための資金の調達や支払い
・業務処理に関する契約責任を負うこと
・単なる労働力の提供ではないこと(機械・設備・資材等の準備や専門的な技術・経験に 基づく業務処理等)
▼弁護士監修の労務・人事分野における書式に雛形集▼
IT業界におけるアジャイル型開発と偽装請負
IT業界におけるアジャイル型開発のようなシステム開発の場合でも、偽装請負が問題となることがあります。
アジャイル型開発とは、「一般に、開発要件の全体を固めることなく開発に着手し、 市場の評価や環境変化を反映して開発途中でも要件の追加や変更を可能とするシステ ム開発の手法であり、短期間で開発とリリースを繰り返しながら機能を追加してシステムを作り上げていくもの」です。
アジャイル型開発においても、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37)」に従い、実態に即して、偽装請負かどうかが判断されます。
もっとも、アジャイル型開発において、偽装請負のリスクを回避するため、過剰な対策や対応が行われることもあり、その有用性を発揮できないという実務的な課題もありました。
そのため、アジャイル型開発と偽装請負に関しては、厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集(第3集)」において、その考え方が具体的に示されています。
例えば、上記応答集では、アジャイル型開発と偽装請負の問題について、以下のとおり、指摘されています。
「アジャイル型開発においても、実態として、発注者側と受注者側の開発関係者(発注 者側の開発責任者と発注者側及び受注者側の開発担当者を含みます。以下同じ。)が対等な関係の下で協働し、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っていると認められる場合には、受注者が自己の雇用する労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行い、また、請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理しているものとして、適正な請負等と言えます。 したがって、発注者側と受注者側の開発関係者が相互に密に連携し、随時、情報の共有や、システム開発に関する技術的な助言・提案を行っていたとしても、実態として、発注者と受注者の関係者が対等な関係の下で協働し、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っていると認められる場合であれば、偽装請負と判断されるものではありません。」
その一方で、「実態として、発注者側の開発責任者や開発担当者が受注者側の開発担当者 に対し、直接、業務の遂行方法や労働時間等に関する指示を行うなど、指揮命令があると認められるような場合には、偽装請負と判断されることになります。」とされており、アジャイル型開発でも、実態によっては偽装請負と判断される可能性が指摘されています。
アジャイル型開発における偽装請負と判断されないためのポイント
・発注者側と受注者側の開発関係者のそれぞれの役割や権限、開発チーム内における業務の進め方等を予め明確にして合意をすること
・発注者側の開発責任者や双方の開発担当者が自律的に開発業務を進めるものであるというようなアジャイル型開発の特徴について認識を共有しておくこと
まとめーIT業界における偽装請負と判断されないためのチェックポイント
①発注者側の開発責任者や開発担当者が受注者側の担当者に対して直接、業務の遂行方法や労働時間を指示していないか?
②受注者側に管理責任者が選任されていたとしても、形骸化しており、実際には発注者側が受注者の担当者に対して、直接指揮命令を行っていないか?
③受注者側の担当者の配置等の決定や変更について、受注者側に裁量が与えられているか?
仮に、上記①、②、③のポイントについて、いずれも疑念が生じる場合、偽装請負と判断されるリスクが高まるため、契約の見直しや現場対応のマニュアルの整備・運用変更も含めて検討する必要があります。
IT業界における偽装請負や労働者派遣については、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約では 問題社員(モンスター社員)対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争対応(解雇・雇止め、残業代、ハラスメント等)、労働審判・労働裁判対応、雇用契約書・就業規則対応、知財労務・情報漏洩、等の労働問題対応を行います。
▼IT業の方向けの顧問サポート▼
大阪で弁護士をお探しの情報通信業(IT業)の方へ
Last Updated on 2025年4月10日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。

代表弁護士 細井大輔 
プロフィールはこちらから