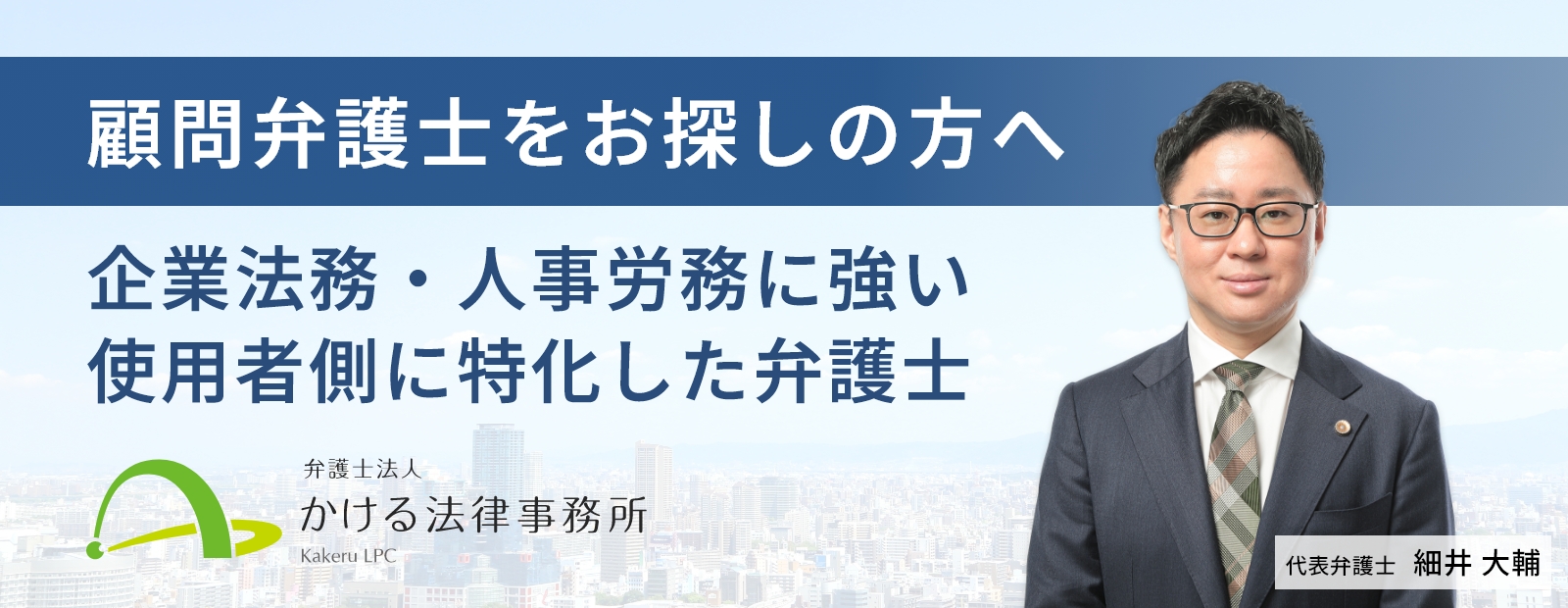

顧問弁護士とは?
『顧問弁護士』とは、企業における紛争・訴訟を解決するだけでなく、組織や事業の特性を踏まえて、未然に紛争・トラブルを予防するためのリーガルアドバイスを行ったり、企業におけるビジネス・取引をスピーディーかつ円滑に進めるための提案を行ったり、契約書等の作成をサポートする弁護士をいいます。
『顧問弁護士』は、企業の持続的な成長の実現に向けて、法的な側面から、企業や経営者に寄り添うパートナーとして、法的リスクを管理し、コンプライアンスを強化するために役立ちます。
『顧問弁護士』の主な役割
- 紛争・訴訟への対応
- 未然のリスクの予防・回避
- リーガルドキュメント(契約書等)の作成・チェック
- スピーディーかつ円滑な取引に向けたリーガルアドバイス
- コンプライアンスの強化
大阪府で顧問弁護士をお探しの経営者の皆様へ ~代表 細井大輔より~

安心できる未来へ、ともにかける
労働人口・生産年齢人口の減少、ダイバーシティマネジメントが求められる現代において、社会や個人の価値観が次々と変化し、課題やリスクも複雑化・多様化しており、予期しない紛争やトラブルも生じます。
特に、労働・人事分野では、生産性向上が求められる一方で、残業代請求、労災、メンタルヘルス、ハラスメント等の個々の労働問題やコンプライアンス違反が経営に重大な損失・リスクを与えます。
労務・人事業務の課題を解決し、組織・事業を成長させるためにも、法律や紛争・トラブルの解決の専門家である顧問弁護士の活用(顧問サービス)を重要な選択肢として、是非一度、検討してください。
弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。
弁護士法人かける法律事務所
代表弁護士 細井 大輔
重大なリスクを回避し、迅速な経営判断を行うために
- 「もっと早く相談していれば、多額の残業代を払わなくてよかったの」
- 「深刻な解雇裁判が起きるなんて想像していなかった」
- 「労働トラブルが頻発し、離職率が高くなり、人材採用が難しくなっている」
トラブル・紛争をきっかけとして、顧問サービスを利用する企業・経営者の皆様が言われるのは、「もっと早く弁護士に相談しておけばよかった」、「長年、順調に事業を続けていたので、このようなトラブルが起きるとは想像していなかった」ということです。
もちろん、順調に事業を続けてきた経営者の皆様の中には、大きなトラブルに発展しなかった、これまで平穏に解決できたという経験を持つ方も多いといえます。
もっとも、労働人口・生産年齢人口の減少、ダイバーシティマネジメントが求められる現代社会では、社会・個人の価値観が大きく変化し、課題も複雑化・多様化しており、重大なリスクが突然、顕在化します。
このリスクが起きたとき、問題が生じた原因や課題を適切に把握し、迅速かつ柔軟に対応しなければ、組織や事業に重大な損失が発生します。
例えば、経営者として、成績が伸びない従業員や他人とすぐ喧嘩する従業員を解雇したいと考えることがあるかもしれません。また、経営不振となり、従業員の人数や給与を見直したいと考えることも当然です。
もっとも、日本の労働法では、解雇や労働条件の不利益変更について厳格な要件や手続を定めています。労働法を意識しないまま、経営者の直感だけで対応してしまうと、裁判や労働組合対応、労働基準監督署対応も含めて、大きなリスク・損失が発生します。
具体的には、正社員を解雇して、それが裁判になり、敗訴してしまった場合、1000~2000万円という費用負担が発生し、事業の継続性に重大な影響を及ぼします。
また、周囲の従業員に与える影響も大きく、人材の定着や採用の観点でも、ブランドや信用を損なわせます。
もし顧問弁護士がいれば、重大な問題を発生させない方法を事前に検討し(予防法務)、問題が発生しても、その問題に迅速かつ臨機応変に対応できます。
例えば、解雇のケースであれば、解雇前に、解雇の有効性を検討し、リスクを踏まえながら、正しい経営判断ができます。もし解雇が難しいと判断した場合でも、他の方法で退職に導くことができないか検討し、企業にとっても、従業員にとっても、win-winの方法で最小限の労力と費用負担で円満に解決できます。
組織や事業が持続的に成長し続けるためには、法律の枠組みやコンプライアンスを無視することができず、法律を最大限活用して、持続的な発展につなげていく必要があります。
顧問弁護士は、企業・経営者の皆様のニーズを把握し、経営において最悪のリスクが起こらないように、企業・経営者の立場にたって、その課題解決に向けた適切な解決策を提案します。
経営に専念し、組織・事業を持続的に成長させるために
「弁護士に相談しなくても、他に相談できる相手がいる」、「弁護士は難しいことをいうので、相談しづらい」ということで、顧問契約が必要ないと考える経営者様もいるかもしれません。
ただ、実際には、顧問先のお客様のほとんどが、「法律のプロに、いつでも相談できるという安心感から経営に専念できる」、「法律の枠組みを参考にできるので、自信をもって経営判断できる」、「リスクを正しく理解できるので、逆にアグレッシブな判断がスムーズにできる」といわれます。
また、企業に顧問弁護士がいれば、従業員の皆様にも、心理的安全性が確保され、本来の業務に集中でき、生産性が向上するという声も頂きます。
特に、労務・人事問題は、本来であれば、組織・事業を一緒に成長させる従業員との間で生じる問題であるため、他の従業員には相談しづらい、また、心苦しい判断が迫られます。
そのため、顧問弁護士に相談することで、法律の枠組みを参考にして、安心感をもって、また、心理的負担が軽減され、よりスピード感をもった経営判断が可能となります。
また、取引先との契約書・合意書を法的に検討したり、新規事業における法的問題点を初期段階から検討できるだけでも、経営判断のスピードがあがり、各担当者の負担は大きく軽減され、生産性が向上します。
弁護士法人かける法律事務所は、「安心できる未来を、ともにかける」をビジョン(理念)として、経営者の皆様が安心して、経営に専念し、組織や事業を持続的に成長させることができるように法律の専門家として、経営者の皆様に寄り添い、サポートさせていただきます。
顧問弁護士として弁護士法人かける法律事務所が選ばれる理由
弁護士法人かける法律事務所は、『安心できる未来へ、ともにかける』を理念として、企業の持続的な成長の実現に向けて、法律のプロフェッショナルとして、質の高いリーガルサポートを提供します。
私たちが顧問弁護士として選ばれる理由は、以下の通りです。
選ばれる理由1幅広い法務分野での対応力
私たちは、「契約法」「労働法」「会社法」「知的財産法」「インターネット法」「独占禁止法・下請法」「個人情報保護法」といった、企業活動に必要となる幅広い法務分野で、専門的な知見や経験を有しています。
そのため、紛争・訴訟対応だけでなく、トラブル・紛争を未然に予防するため、法律のプロフェッショナルとして、総合的な知見や経験を踏まえたアドバイスや提案が可能です。
選ばれる理由2スピードや柔軟性を重視した提案力
企業活動で発生する法的課題を解決するためには、迅速な対応や複雑な利害関係に対する柔軟な対応力が求められます。私たちは、お客様が希望するコミュニケーションツール(Eメール、Chatwork、LINEWORKS等)を利用して、スピーディーに対応することは、もちろん、法律の枠組みを杓子定規にあてはめず、企業や事業の特性に応じた臨機応変な対応を日々心がけています。
選ばれる理由3企業や経営者に寄り添ったアプローチ
私たちは、企業や経営者に寄り添い、現実的な対応策を提案することを目指しています。特に、労働・人事トラブル対応では、企業側の相談に特化しており、労働者側の相談を受け付けていません。あくまで企業法務に注力する法律事務所として、企業の持続的な成長に貢献します。
企業や経営者の視点に立って、紛争・トラブルを未然に予防できるように、また、紛争やトラブルが顕在化した場合でも、企業の生産性の向上を意識しながら、問題解決に努めます。
選ばれる理由4チームで支える充実したサポート体制
弁護士法人かける法律事務所は、複数の弁護士やパラリーガルが所属しており、チームで対応することによって、迅速かつ継続的なサポートを可能としています。
また、相談やトラブル内容に応じて、その分野を得意とする弁護士が対応するため、適切な解決が可能となります。
選ばれる理由5明確で柔軟な料金プラン
弁護士法人かける法律事務所の顧問サービスでは、企業のニーズに応じたプランを複数用意しており、透明性の高い料金体系で、法務コストの予算管理をサポートできます。
顧問契約の最低期間は6か月となっていますが、その後は1か月ごとの自動更新になりますので、企業のニーズに応じて料金プランを設定できます。
選ばれる理由6実績に基づく信頼と安心感
私たちは、これまでに多くの企業の顧問弁護士として、豊富な実績を積み重ねてきました。現在では、業種や地域を問わず、50社以上の企業様との間で顧問契約を締結しており、日常的に発生する法的課題に向けた助言やチェックを行っています。
年々、顧問サービスに関する問合せも増えており、顧問先企業様との中長期的な関係を構築し、顧問先企業様が持続的な成長を実現できるよう、リーガルサービスを提供しています。
当事務所の顧問弁護士費用について
顧問契約の料金表(通常プラン)
顧問プランは、ライトプラン(月額5万円・税別)、スタンダードプラン(月額10万円・税別)、プレミアムプラン(月額15万円・税別)の3種類を準備しています。また、お客様のニーズや依頼内容に応じて、「カスタマイズプラン」も提案できますので、是非お問い合わせください。
| プラン | プラン名 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金(税別) | 5万円/月 | 10万円/月 | 15万円/月 | |
| サポート内容 | 対応時間 | 2時間 | 5時間 | 10時間 |
| アドバイス | 電話・Eメール・LINE・Chatwork | 〇 | 〇 | 〇 |
| 法律相談 | 面談又はオンライン | 〇 | 〇 | 〇 |
| AI契約書レビュー | AI契約書レビューシステムによる契約書チェック | 〇 | 〇 | 〇 |
| 契約書・規約 | 弁護士による契約書チェック | 〇 (月1通) |
〇 (月2~3通) |
〇 (月3~5通) |
| クレーム対応 | 窓口対応 | × | 〇 | 〇 |
| 債権回収 | 簡易な内容証明郵便・警告書(弁護士名) | × | 〇 | 〇 |
| グループ会社対応 | グループ会社対応へのアドバイス・相談対応 | × | × | 〇 |
| 優先対応 | 緊急案件への優先対応 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 顧問弁護士外部表示 | 御社販促物への掲載 | × | 〇 | 〇 |
| 弁護士費用割引 | 着手金及び報酬金の割引 | 5% | 10% | 15% |
- ×:別費用
- 〇:対応可能
- ①顧問料は当月分を前月25日までに支払います。ただし、自動引落(NSS日本システム収納)の口座振替日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
- ②顧問契約の最小期間は6か月間となり、その後は1か月ごとの自動更新となります。顧問契約の終了を希望される場合、終了希望月の前月末日までに通知ください。通知日の翌月末日で顧問契約が終了となります。
- ③支払済み顧問料はお客様の都合により返金できません。
- ④事務所を離れて業務が必要となる場合、別途、出張日当が必要となります。
- ⑤債権回収で解決した場合、別途、報酬金が必要となります(弁護士費用割引あり)。
- ⑥紛争・裁判対応が必要となる場合、別途、弁護士報酬が必要となります(弁護士費用割引あり)。
- ⑦対応時間を超過する場合、タイムチャージ方式となります。超過分のタイムチャージは、代表・パートナー弁護士が30,000円(税別)/時、シニアアソシエイト弁護士が25,000円(税別)/時、ジュニアアソシエイト弁護士が20,000円(税別)/時、パラリーガルが15,000円(税別)/時となります。
- ⑧弁護士法人かける法律事務所の弁護士報酬規定は、随時変更することがあります。
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
【顧問サービスの内容】、【顧問弁護士のメリット】は、こちらを確認ください。
顧問プランは、ライトプラン(月額5万円・税別)、スタンダードプラン(月額10万円・税別)、プレミアムプラン(月額15万円・税別)の3種類を準備しています。また、お客様のニーズや依頼内容に応じて、「カスタマイズプラン」も提案できますので、是非お問い合わせください。
顧問契約の料金表(労働問題対応・注力プラン)
| プラン | プラン名 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金(税別) | 5万円/月 | 10万円/月 | 15万円/月 | |
| サポート内容 | 対応時間 | 2時間 | 5時間 | 10時間 |
| アドバイス | 電話・Eメール・LINE・Chatwork | 〇 | 〇 | 〇 |
| 法律相談 | 面談又はオンライン | 〇 | 〇 | 〇 |
| 労働組合対応 | 窓口・代理人対応や団体交渉への立会 | × | 〇 | 〇 |
| 窓口・代理交渉 | 裁判外交渉の窓口・代理人対応 | × | 〇 | 〇 |
| 就業規則・雇用契約書 | チェック・アドバイス | 〇 | 〇 | 〇 |
| グループ会社対応 | グループ会社対応へのアドバイス・相談対応 | × | × | 〇 |
| 優先対応 | 緊急案件への優先対応 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 顧問弁護士外部表示 | 御社販促物への掲載 | × | 〇 | 〇 |
| 弁護士費用割引 | 着手金及び報酬金の割引 | 5% | 10% | 15% |
- ×:別費用
- 〇:対応可能
- ①顧問料は当月分を前月25日までに支払います。ただし、自動引落(NSS日本システム収納)の口座振替日は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
- ②顧問契約の最小期間は6か月間となり、その後は1か月ごとの自動更新となります。顧問契約の終了を希望される場合、終了希望月の前月末日までに通知ください。通知日の翌月末日で顧問契約が終了となります。
- ③支払済み顧問料はお客様の都合により返金できません。
- ④事務所を離れて業務が必要となる場合、別途、出張日当が必要となります。
- ⑤労働組合対応や労働トラブル対応について、代理人対応によって解決した場合、別途、報酬金が必要となります(弁護士費用割引あり)。
- ⑥紛争・裁判対応が必要となる場合、別途、弁護士報酬が必要となります(弁護士費用割引あり)。
- ⑦対応時間を超過する場合、タイムチャージ方式となります。超過分のタイムチャージは、代表・パートナー弁護士が30,000円(税別)/時、シニアアソシエイト弁護士が25,000円(税別)/時、ジュニアアソシエイト弁護士が20,000円(税別)/時、パラリーガルが15,000円(税別)/時となります。
- ⑧弁護士法人かける法律事務所の弁護士報酬規定は、随時変更することがあります。
当事務所の解決事例について
弁護士法人かける法律事務所の解決実績について下記ページにて紹介をしております。
解決事例1問題社員対応:不正行為(横領)を行った従業員に損害賠償を請求し、被害金額を回収した事例
従業員が会社のシステムを利用し、お客様に対してシステム利用料金を請求していたが、会社名義の口座ではなく、その従業員の関係者の口座に振り込ませていたことが発覚した。その金額合計は約1000万円である。不正行為が発覚したことについて、当該従業員には、まだ伝えていないが、会社としては、被害金額を回収したい。
⇒弁護士による対応内容と対応後の状況
- ①まず、不正行為の態様と被害金額を特定し、証拠を確保する。
- ②会社の代理人として、不正行為を行った従業員と面談し、被害弁償を求める。
- ③被害金額を回収する。
- 不正行為の態様や被害金額を特定し、証拠も確保していたため、不正行為を行った従業員も面談において、すぐに不正行為を認め、被害弁償を約束した。
- 被害弁償の支払方法についても話し合い、その従業員の親族も交えて話し合いを行い、一括で被害弁償金の支払を確保できた。
解決事例2競業避止義務違反対応:退職した従業員による競業避止義務違反に対応した事例
退職した複数の従業員が、同一の商圏内において、会社と同様のサービスを始め、お客様(利用者)や取引先との接触を開始している。会社は、就業規則において退職後の競業避止義務を定めており、また、入社時・退職時に誓約書も取得している。
退職した複数の従業員は、雇用契約に基づく競業避止義務に違反しており、何らかの対応ができないか。
⇒弁護士による対応内容と対応後の状況
- 会社の代理人として、内容証明郵便を利用して、退職した複数の従業員に対して、競業避止義務に違反していることを通知し、改善を求めました。
- 退職した複数の従業員から、すぐに連絡があり、競業避止義務の内容を確認するとともに、新たにサービスを始めるうえでのルール・条件を確認し、会社の利益が侵害されないことも確認できたため、話し合いによって解決いたしました。
解決事例3就業規則対応:従業員への金銭貸付のための借用書を作成した事例
従業員が引っ越しのための費用がないということで相談を受け、何とかしてあげたいので、お金を貸してあげたい。ただ、口約束では問題が起きたときに不安があるため、その対応方法を知りたい。
⇒弁護士による対応内容と対応後の状況
- 貸付条件(返済条件)を検討し、契約書(借用書)を作成し、金銭の貸付内容を明確にして、今後のトラブルを回避する。
- 貸付条件(返済条件)を確認し、契約書(借用書)を作成した。
顧問先業種一覧
弁護士法人かける法律事務所の顧問サービスを利用していただいているお客様(顧問先企業)の業種は、建築・不動産業、製造業、運送・運輸業、卸売業、小売業、IT・ウェブ関連会社、情報通信業、人材派遣業、医療法人・病院、訪問看護事業、福祉・介護事業、出版・印刷業、飲食業、美容業、アパレル業、サービス業、教育・学習支援事業、ソーシャルアクション事業等様々あります。
特に、注力している業種や分野は、以下のとおりです。
*企業規模別のニーズに応じた対応も可能です。例えば、『セカンド顧問』として、労務・人事問題に特化し、日常的な労務・人事トラブルを気軽に相談するための顧問サービスも提供しています。
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
よくあるご質問
Q.顧問弁護士は、企業において、どのような役割を果たしますか?
『顧問弁護士』とは、企業における紛争・訴訟を解決するだけでなく、組織や事業の特性を踏まえて、紛争・トラブルを未然に予防するためのリーガルアドバイスを行ったり、企業におけるビジネス・取引をスピーディーかつ円滑に進めるための提案を行ったり、契約書等の作成をサポートする弁護士をいいます。
『顧問弁護士』は、企業の持続的な成長の実現に向けて、法的な側面から、企業や経営者に寄り添うパートナーとして、法的リスクを管理し、コンプライアンスを強化するために役立ちます。
『顧問弁護士』の主な役割
- 紛争・訴訟への対応
- 未然のリスクの予防・回避
- リーガルドキュメント(契約書等)の作成・チェック
- スピーディーかつ円滑な取引に向けたリーガルアドバイス
- コンプライアンスの強化
Q.企業が顧問弁護士を導入するメリットについて教えてください。
企業活動において紛争・訴訟が発生した後に、弁護士を探して依頼したとしても、企業や事業の特性を十分に理解されないまま、提案や問題解決が行われたり、そもそも企業法務に精通する弁護士を探すこと自体が困難なケースも多くあります。
顧問弁護士がいれば、このような手間や労力を回避することが可能ですし、企業や事業の特性を反映した問題解決が可能となります。
また、顧問弁護士がいれば、紛争・トラブルを未然に予防するためのアドバイスを受けることができたり、スピーディーかつ円滑に取引を進めるための提案を受けることもできます。
重要な取引において契約書を作成する場合でも、重大なリスクを回避するための取引が可能となります。
重大なリスクを回避したり、トラブルを未然に予防するためにも、企業が顧問弁護士を導入するメリットがあります。
Q.顧問弁護士を導入すれば、どのようなトラブルを予防できますか?
例えば、労務・人事トラブルにおいて、労働法を知らないまま、経営者の直感で対応してしまうと、労働トラブルが深刻化してしまい、多額の金銭の支払を余儀なくされたり、問題社員が復職する等多大な損失を被ることがあります。
また、重要な取引を開始する前に契約書をチェックしておかないと、不利益な取引や条件を余儀なくされてしまうことがあります。
さらに、コンプライアンス意識が十分でない場合、誤った法令解釈等によって、重大なコンプライアンス違反が発生し、企業の信用やブランドが低下してしまうこともあります。
顧問弁護士を導入し、顧問サービスを活用することによって、重大な紛争・訴訟を回避できたり、取引トラブルを未然に予防することができますし、コンプライアンスを強化することで、企業の信用やブランドを確保できます。
Q.顧問弁護士は、どのような企業に必要ですか?
顧問弁護士は、あらゆる規模・業種の企業にとって有益ですが、以下の状況にある企業には、特に必要だと考えられます。
1.専任の法務担当者や法務部門が存在しない企業
自社で専任の法務担当者や法務部門を有しない企業は、外部の顧問弁護士を活用することによって法務機能を補完することができますし、重大なリスクを回避し、紛争・訴訟を未然に予防することが可能です。
特に、専任の法務担当者や法務部門を自社で抱えることは、多額なコストが必要なうえ、優秀な法務担当者を採用することも、簡単なことではありません。そのため、顧問弁護士を活用することによって、リーズナブルな法務コストで、法務部門の役割を補完することができます。
また、これから専任の法務担当者や法務部門を設置したいという会社でも、顧問弁護士を活用することによって、法務担当者の育成や教育も可能です。法律の専門家である弁護士と一緒にプロジェクトを担当することによって、法的な枠組みや法律の基本を習得することができます。企業内のノウハウ・経験の蓄積にも役立ちます。
2.事業拡大を目指す成長企業
新規事業の立上げを積極的に行っていたり、M&Aを計画的に実行する成長企業においては、新規の取引や紛争・トラブルも増加するため、重要な取引に関する契約書のリーガルチェックや、紛争・トラブルを未然に防止するための法的アドバイスを受ける必要性が高まります。
顧問弁護士を活用することによって、法務管理コストを抑え、企業や事業の特性に応じて、実際に役立つアドバイスを受けることができます。
3.コンプライアンスを強化したい企業
コンプライアンス違反や不祥事は、企業や事業に重大なリスクや損失を与えます。顧問弁護士を活用することによって、社内のコンプライアンス教育体制を整えることができますし、役員も従業員も、コンプライアンスを意識しながら、事業活動を遂行することができます。
コンプライアンスを強化したい企業においては、顧問弁護士は必要不可欠といえます。役員や従業員が安心して事業を進めるためにも、顧問弁護士の活用を検討してください。
4.人事・労務管理の課題を抱える企業
多数の従業員を抱える企業においては、人事・労務管理トラブルをゼロにすることはできず、また、深刻なトラブルやリスクを回避する必要があります。
また、優秀な人材を育成し、定着してもらうためにも、労働法を遵守して、問題社員対応や雇用契約・就業規則等の仕組みを整備することが必要です。
人事・労務管理の課題を抱える企業では、顧問弁護士を活用することによって、深刻な労働トラブルを回避することができます。労働問題を数多く取り扱う顧問弁護士に依頼することによって、深刻な労働トラブルが回避され、経営者は、本質的な業務に専念できるので、持続可能な事業活動を実現できます。
Q.顧問弁護士は、どのような業務に対応してくれますか?
顧問弁護士が対応可能な業務やサービスは、以下のとおりです。
- 法律相談(電話、Eメール、チャット等)
- 契約書の作成やレビュー
- 労務・人事トラブルへのアドバイス
- クレーム対応のアドバイス・窓口対応
- コンプライアンス研修・セミナー対応
*紛争・訴訟対応も可能ですが、別途、委任契約の締結が必要となります。
Q.スポット(単発)と顧問契約で弁護士を利用する場合の違いについて、教えてください。
スポット(単発)の場合、まずは弁護士を探して、法律相談(有料)を設定し、個別に見積を行ったうえで、依頼の可否を決めることになります。この際、法律相談の設定までに2~3週間を要する場合があったり、相談内容の状況や相談時期によっては、そもそも依頼を引き受けてもらえない場合もあります。また、法律事務所(弁護士)も、企業や事業の内容・特性を十分に把握していないため、スピーディーかつ臨機応変な対応が難しいこともあり、法律を杓子定規に適用したアドバイスしかできない場合もあります。
これに対して、顧問弁護士では、紛争・訴訟が発生した場合、スピーディーに法律相談を設定することが可能であり、受任の可否もすぐに決めることができますし、紛争・訴訟の解決に向けて、現実的で柔軟なアドバイスをもらうことができます。また、弁護士費用もスポット(単発)と比較すると、リーズナブルな価格で依頼することも可能ですので、ケースによっては、顧問料の範囲内で対応することもできます。
何よりも、顧問弁護士では、中長期的な関係の構築を前提としているため、企業や事業の特性に応じたアドバイスを受けることができたり、臨機応変な対応が可能です。企業が実際に希望する解決方法を実現するためにも、スポット(単発)ではなく、顧問弁護士の活用を推奨します。
Q.労働問題や労働トラブルへの対応でも顧問弁護士は役立ちますか?
まず、顧問弁護士であれば、労働紛争や労働訴訟が顕在化する前から相談できるので、労働法の視点から、労働紛争や労働訴訟を回避できるようなアドバイスが可能です。
多くの労働問題では、事前のアドバイスや提案によって、紛争・訴訟が顕在化する前に解決できます。万が一、労働紛争や労働裁判に発展した場合でも、従前の対応方法や会社の方針を理解しているため、会社の希望に即した迅速な対応も可能です。
また経営者の立場からすると、労働問題は、他の従業員に相談しづらい状況にある場合も少なくありません。顧問弁護士であれば、労働法の観点から、企業・経営者に寄り添ったアドバイスが可能ですので、経営者の負担を軽減できます。
顧問弁護士は、労働問題の予防、初期対応や解決のすべての段階において対応が可能であり、企業や経営者に寄り添ってサポートします。
Q.企業の法務部と顧問弁護士との連携内容について教えてください。
企業に法務部門が存在する場合でも、外部の弁護士との連携や協力が必要となる場合があります。例えば、紛争・訴訟対応が必要となった場合には、外部の弁護士に依頼することが必要です。
また、複雑で専門性が必要な取引や契約書では、企業の法務部門が外部の弁護士と連携することで、スムーズな取引が可能となります。また法務管理コストをコントロールすることができるので、リーズナブルな費用で、企業のリスクを最小化することも可能です。
さらに、法務部門では対応できない専門的な問題や負担の大きい業務について、外部の顧問弁護士を活用することで、専門知識を補完したり、リソース不足を解消できます。
また、企業において、コンプライアンス研修やハラスメント防止研修を開催する場合でも、法務部門と顧問弁護士が企画段階から連携することにより、企業のニーズに対応した効果的な研修が可能となり、コンプライアンスが強化されます。
企業の法務部門と顧問弁護士が密に連携協力することによって、会社の安心や持続的な成長を守ることができます。
Q.顧問弁護士を選ぶときの注意点について、教えてください。
顧問弁護士を契約する際、自社が必要としている業種や法分野に対応できる弁護士が所属しているかどうかを確認する必要があります。例えば、弁護士といっても、一般民事(離婚、交通事故等)を得意とする弁護士や、企業法務を得意とする弁護士がいます。また、労働分野に精通する弁護士でも、労働者側が得意な弁護士と、企業側が得意な弁護士がいるので、弁護士の専門性や対応分野を確認しておく必要があります。
また、企業の担当者が希望するコミュニケーションツール(チャットワーク、LINE、Eメール、ZOOM、Teams等)について、法律事務所側が対応しているかどうかという点も重要です。利用できるコミュニケーションツールによって、迅速かつ円滑に相談できるかどうかが変わってきます。相談しやすいか、また、スピーディーなレスポンスがもらえるか、という点は、顧問弁護士を選ぶうえで、とても大切です。
さらに、相談内容に対する対応標準期間も事前に確認しておく必要があります。契約書のチェックでも、1~2営業日で対応する事務所もあれば、1~2週間を要する事務所もあります。企業側が必要とする納期で対応してもらえるのか、事前に確認しておくことでミスマッチがなくなります。







